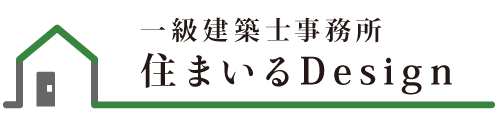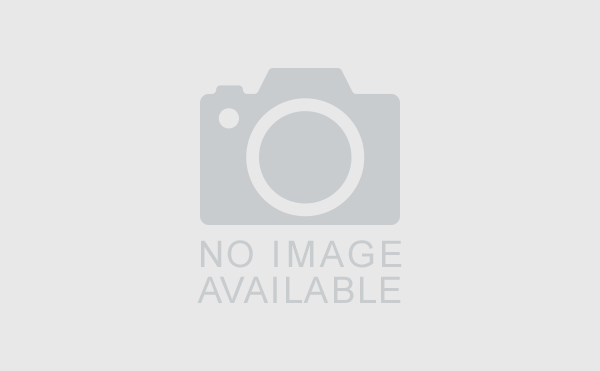「強・用・美」を提供する

高校の2年間は、理系クラスだったこともあり、大学受験では工学部や理学部が視野に入っていました。芸術系は「センスや能力」だけが見られるような気がしており、そこに自信が持てませんでした。医学系は命に直接係わることが怖かった。そして、理学部は永遠に研究や実験をしていかなければならないような気がしていました。最終的に「建築学科」に絞ったのは、「デザインと技術、活用」が混在しており、努力次第で自分でもできるのではないかと思ったからです。結果、大学の4年間だけでなく、今でも建築や住宅が生業となっているのです。
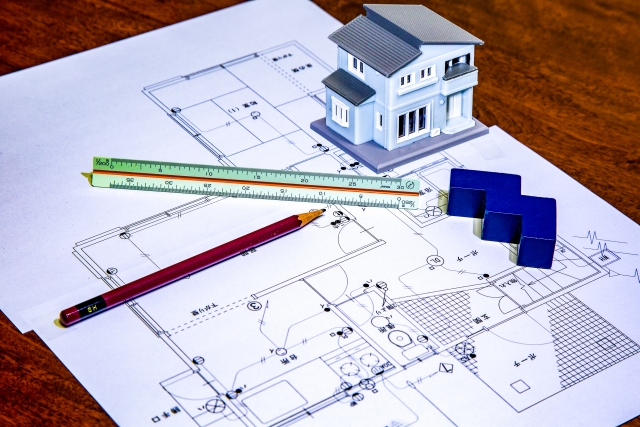
建築を学ぶ際に最初に学ぶ言葉の一つが、建築の三大要素である「強・用・美」です。これは、今から2000年以上前、古代ローマの建築家であるウィトルウィウスが提唱した建築の原理で、その著書「建築書」において、「強がなければ用は果たせない、強と用がなければ美は形だけのもの、そして、美がなければ建築とはいえない」という一文を残しています。もともと、「自然環境から自分の身、家族、財産、生活、休息」を守るといった機能から、建築物はつくられたのではないでしょうか。それが、生活をする中で、使いやすいといった機能を求めはじめ、最後に「他人が見ても美しい」を求めるようになったのでしょう。建築全般に広げると、作業、会合、スポーツ、娯楽といった機能を持つ建物が、時代とともに増えていきました。

しかし、いつの時代でも、どのような建築でも「強・用・美」は必要不可欠ですが、そこにも優先順位があり、やはり住む人と財産を守る「強」が、建築物にとって最も大切な役割だと感じるのです。私自身、阪神・淡路大震災をきっかけに、木造住宅の耐震化への意識が高まり、「地震から命を守る」ことの重要性に気づきはじめたのです。

その後、木造住宅の建築構造事務所に異動し、構造計算に携わるようになったのですが、工務店様から送られてくるプランが、残念ながら構造的に不安定なものばかりなのです。構造を理解しないで構造計算(許容応力度)をすると、無駄な材料、基礎形状、金物を使うことになり、コストアップにつながることになります。「こんな基礎つくれるか」といった苦情が入るので、「○○のように間取りを変えてください」と話しますが、「お客様に言えない、変えられない」となるのです。そこで、住宅プランナーを集め、構造勉強会「コストダウンできるプランづくり」「許容応力計算のポイント」などについて、事例を交えて実施していったのです。非常に喜んでいただいていたのですが、残念ながら、構造計算事務所を廃業することとなってしまいました。現在は、他の構造事務所が「構造塾」という研修会を実施していますので、そちらを受講することをお勧めしています。

また、N社に在籍中、50歳を過ぎたころ、分譲住宅や注文住宅だけでなく賃貸住宅も提供していましたが、全ての建物に対して「許容応力度計算」を義務付けたのです。社員も構造計算を義務付けられると、それを理解しないとお客様に良い提案ができないとなり、木造建築の構造はどうあるべきか、学んでいったのです。そして、社員にとっても自信になり、「構造計算付」を商品の前面に出すことで、他社との差別化にもなっていったのです。

年齢を重ねたこともありますが、建築にはいろいろな要素が含まれていると一層感じるようになりました。やはり、この「強・用・美」全ての要素を兼ね備えることが、住宅プランナー、建築設計士にとって、重要なのではないでしょうか。