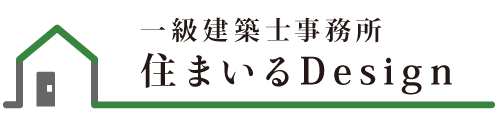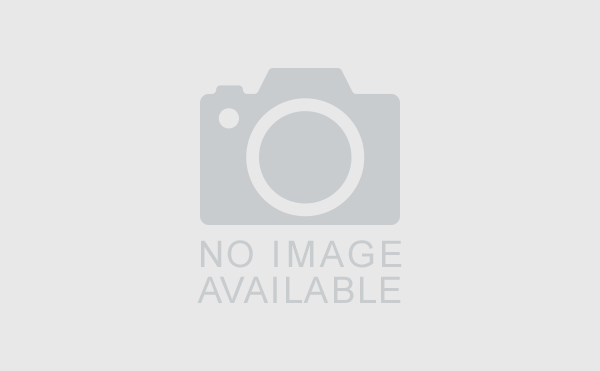東日本大震災直後、仙台へ向かう(1)
NPO法人住まいの構造改革推進協会(住構協)を運営していたこともあり、大きな地震があると3日目の夜には、被災地に入る活動をしていました。倒れた家と倒れなかった家を比較し、その原因を調査するためには、早期に入らないと片付けが始まるからです。中越地震(2004年)、中越沖地震(2007年)、能登半島地震(2007年)などを経験しましたが、最も記憶に残っているのは、言うまでもなく、2011年の東日本大震災です。

3月11日は、住構協の事務局でもあった横浜にあるN社の本社ビルで一般的な業務をこなしていました。発災時には、仕事を止めて直ぐに机に伏せた後、防災委員の指示で避難階段を降りて外部に避難したのです。その時に電柱をはじめ、高い建物がゆっくり揺れているのを見て、さらに、震源は東北と聞いて、これは中途半端な地震ではないと感じ、関係者に「東北では、とんでもないことが起きている可能性がある」と叫んだ記憶があります。そして、それから数時間後には対策本部を設立、数日間、事務所に泊まり込むことになったのです。当日は、帰宅困難者を受け入れ、非常食や毛布を準備、そして、東北にいる約100人の社員とその家族の安否確認を集中して行いました。次の日には、ある程度は交通網の情報が集まり、新潟にあるN社の木材市場を起点に、東北6県にいる社員、家族を助けるために動くことになったのです。私は、物資をもって最初に東北・仙台に行くリーダーとして、新潟に向かいました。

3日目には、警察から震災支援車の許可をもらい、4トントラックとワンボックスカーに物資を詰め込み、会津、郡山経由で仙台を目指しました。しかし、新潟を出て福島県に入るころ、対策本部からの指示が「郡山でなく、山形経由で向かえ」と変わったのです。郡山にはたくさんの同僚(同じ事業部の戸建住宅メンバー)がいたので、寄りたい気持ちが大きかったことに加え、山形経由は雪が降り、高速道路もなく、決して良い状況ではなかったので、当時は不思議で仕方ありませんでした。その後に聞かされたのですが、「原発事故」が起き、郡山まで影響が出る可能性があるため、「支援車を巻き込む訳にいかない」という判断だったのす。また、対策本部では福島県の社員をどう避難させるのか、議論が続いていたというのです。

山形県に入ると、ガソリンスタンドに車の長い行列ができており、数時間たっても解決できる状況ではありませんでしたが、警察の「金看板」付きの支援車は優先的に給油していただき、一般車両通行止めの高速道路などにも入れていただけました。積雪が酷い中でしたが、15時間ほどかかり、宮城県に入ることができました。新潟を朝7時に出発したにもかかわらず、夜までかかってようやく宮城県に入ることができました。宮城県に入ってからは状況が大きく変わり、どこをどのように進んでいけばいいのか、手探り状態で道を探して進んでいったのです。コンビニや外食店もほとんど閉店しており、まともに食事もできる状況ではありませんでしたが、それでも何とか深夜2時には宮城市場がある大衡村に着きました。待ちに待っていた社員と会った時には、お互い歓声を上げたほどでした。水や食料、服やエネルギーなど、数十人が一週間程度は生活できる量は積んでいましたが、ガソリンをはじめ、不足している物がまだまだ多く存在していました。新潟市場には、全国のN社の営業所、木材市場から、今後不足すると考えられる物資や建材などが続々と集まりだしており、第二弾が来ることを伝え、その日は、宿泊施設がある山形まで戻ったのです。長い一日が終了したのは、次の日の早朝でした。

明るくなってから、プレカット工場のある多賀城に向かったのですが、まだ津波の水も残る中、残材やひっくり返った車、壊れた店舗に唖然としました。屋根の上まで津波が来たプレカット工場は、近づくことができないほどの壊れ方でしたが、それでも、そこで働く社員は全員避難が間に合い、一人の被害者も出さずに済んだのです。そして、被災者である社員の声を聴くことになったのです(続く)。