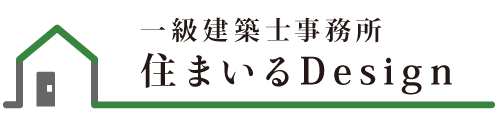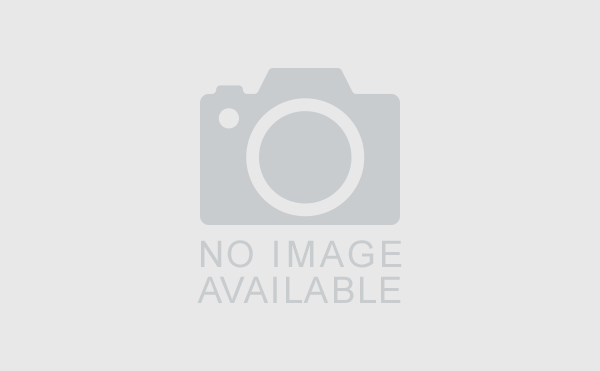建築協定や用途地域制限は、時代に合っているのか?
定年が近くなり、中学校、高校の友人たちと頻繁に会うようになりました。子育てが終了し、仕事も身体も自由になる人が多くなるからです。介護が始まる時期ではあるものの、健康でアクティブな人たちは良く集まってくれています。「耐震・断熱体験館」に来ては、おしゃべりとお酒を楽しむ人たちが多くなっています。

そのような中、地元では有名な「高級住宅タウンの家」をバブル時代に買った友人が、奥様の実家が近い東京のマンションを購入し、引っ越しをすることになっていたのです。しかし、自宅が1年以上売れないので、何とかならないかと相談してきたのです。残念ながら、その地域は、住民が高齢化し、小学校、中学校、スーパーも閉鎖してしまったのです。かろうじてバス便はあるもののJRの駅までは遠く、上り坂があるのです。おまけに建築協定が存在し、隣地境界や道路境界から数メートルは植栽の指定があり、維持管理費が非常にかかってしまうような住宅地なのです。土地も大きいのに分割できず、専用住宅でしか利用できないなどの縛りがある上、建蔽率が30%と低いのです。

当時、優良な住環境を維持するため、良かれと思い建築協定がつくられましたが、転売や高齢者の住まいとしては大きな足かせになっていたのです。分割できれば、2棟の分譲住宅にして若い世代が購入する可能性があるし、アパートやグループホーム、ゲストハウスに利活用できれば、購入客の幅は増えるのです。結果、不動産価値が維持できるどころではなく、大きく下がる現象が起きているのです。それでも何とかしようと動いたことで、中古再販事業者に、安い価格ですが購入していただけたのです。その会社は、リフォームして再販していますが、残念ながら1年近くたっても販売できていないのです。売るときには、「こんな安くなるのか」と悩んでいましたが、あの時背中を押して決断していただいたのは成功だと思っています。こうしたニュータウンは、同じ世代が一気に購入し、同時に子育てが終わり、同時に高齢化していく。街の活気が一気に失われていくのです。残念ですが、そのような住宅政策であったとあきらめるしかないのです。

戦後、住宅不足が深刻で、政策としてどんどん家をつくってきました。ニュータウンをはじめ、集合住宅(マンション)、社宅、住宅ローンなどは、社会問題を解決することに大きく貢献してきました。しかし、現在は、住まいは供給過多になり、人口減少、少子化、世帯人員の減少(単身世帯の増加)などが進んでいます。社会における課題や問題が変わってきているのに、私たちが変わろうとしなくていいのでしょうか。街や地域は、いろいろな世代が混在していた方が賑わいを失わないのです。昔のように、相続して後継ぎが引き継ぐのであればよいのですが、赤の他人や法人が引き継いでいきますから、使い方が大きく変わるのは当然のことだと思います。住宅地の中に、小さな店舗や作業所、介護施設会社などが入ってきてもいいと思うのです。住民の快適な生活も確保しながら、建築物(住宅)がもっと活躍できるようにできれば、活気も維持され、資産も確保できるはずです。

そろそろ、高度成長時代から続く「住宅すごろく」を終焉させる時期に来ています。住まいは、「子育て環境」だけでなく多様化する必要があると考えています。車が、所有からシェアカーに変わったように、住まいも仕事場であり、介護施設、シェアスペースにしていかなければならないと考えています。時代とともに、利用ニーズが変わっても対応できる建築物が必要ではないでしょうか。それが永く利活用され、社会のために役に立つということではないでしょうか。どの時代も家族を守るために、住まいは必要不可欠ですが、日本の社会情勢によって、法律やルールは変えるべきなのです。私たち人間がつくったルールで、変えることを拒み、自分たちで首を絞めるような理由はないのです。まずは、住民で決めることのできる建築協定を見直してみませんか。それだけでも、未来は大きく開けると思います。住宅政策を変えることで、いろいろな生活スタイルが選択できるようにすべきだと感じています。