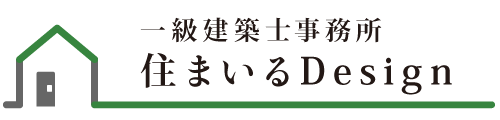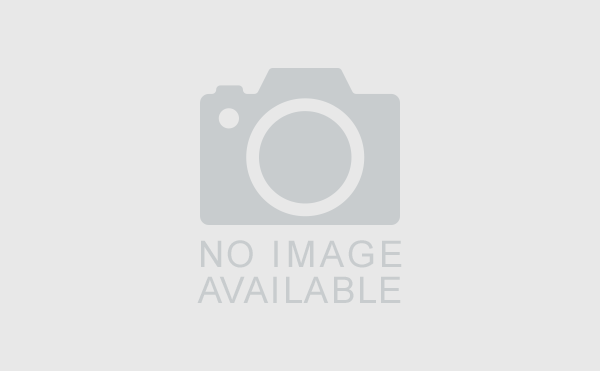木造建築の遮音性能をどう解決するか

新築住宅の着工戸数が落ち込んでいる一方、木造非住宅の新築は増加傾向にあります。アパートや介護施設、グループホームだけでなく、店舗、事務所、倉庫など、2階建てまでならば、コストパフォーマンスの良さで選ばれているようです。住宅の総合展示場でさえも、そのような建物に関する知識がないと対応できなくなっています。また、これまで大きな建物しか相手にしていなかった地場ゼネコンやハウスメーカーも、小さな建築物(彼らにとって)をターゲットにしてきています。今後はさらに、上記のような非住宅建築は、木造のシェアが高まり、競争になってくると思います。
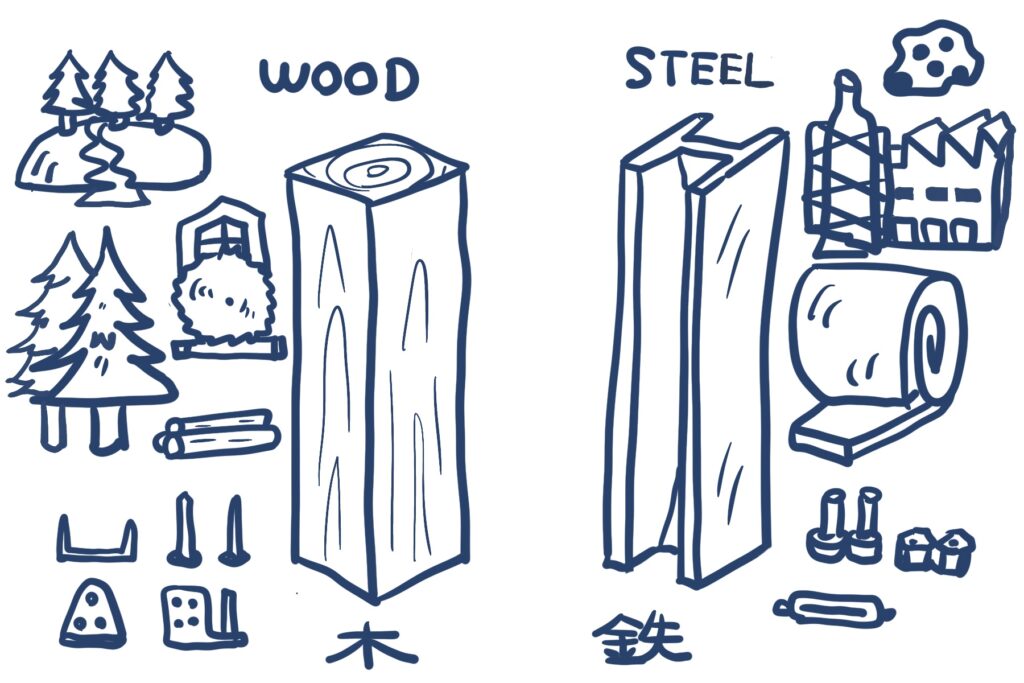
木造建築が有利な点は、コストだけでなく、耐震性や断熱性にもあります。躯体が軽いということは、地震力を受けにくいということです。また、木材の特性から、躯体そのものが断熱性能を持っていることも強みです。一方で、最大の課題が遮音性能です。特に、重量衝撃音は止めにくく、どのメーカーも苦労しながら対策を考えています。私は、アパートの受注を手掛けるようになってから、基本的にはメゾネット型を設計し、上下階を同じ家族で住む間取りにしてきました。それだけ、木造建築で遮音性能を高めることの難しさを知っていたからです。しかし、貸店舗、事務所などを手掛けるようになると、機能性が第一であり、上下階で別法人が使用するプランをつくることになります。その場合は、ALCメーカーやプラスターボードメーカーの推奨仕様を採用していました。コンクリート打設をするような工法などと比較すると、十分な性能は担保できない状況です。

私自身が音の専門家ではないので、これまでは間取りの工夫で補うしかないと考えてきました。専用住宅がほとんどであったため、一階に音が出ても影響のないスペース(玄関や収納、水回り)を増やしたり、リビングや寝室、書斎の上には居室をつくらないようにしてきました。しかし、専用住宅以上に難度の高い建築が増えているため、間取りの工夫だけでは対応できなくなってきています。だからこそ、木造建築業界として、遮音部材の開発や新しい設計手法を確立させなければならないと思うのです。そうすることで、建築物の木造化率が大幅に高まると期待しています。
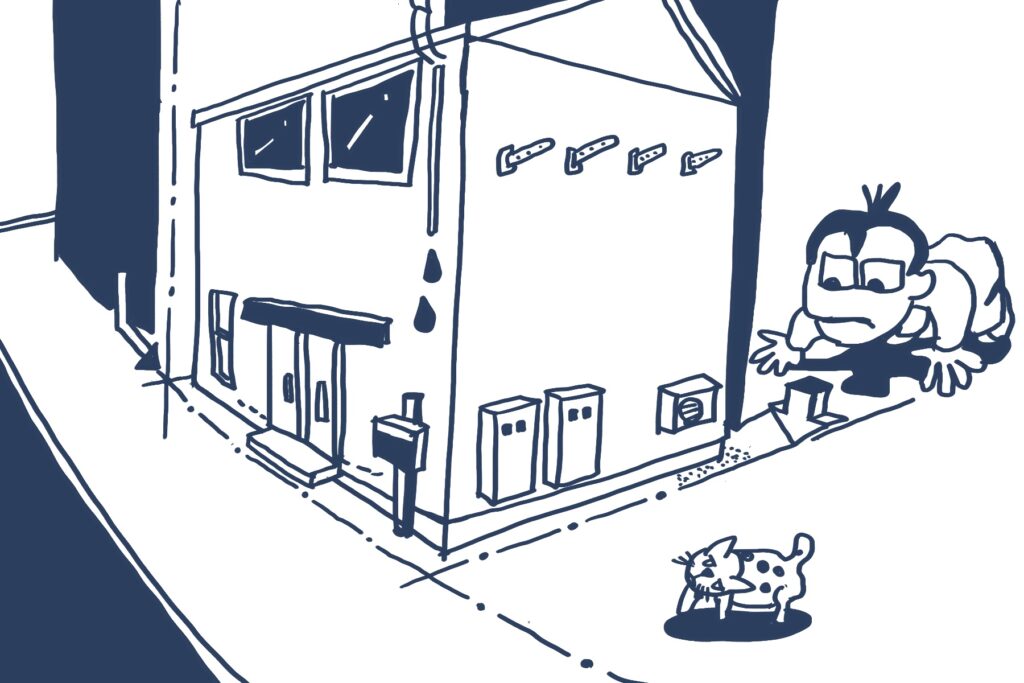
そのような中、音は振動であることから、その振動を抑えることで音を和らげる方法が合理的だと思います。木造建築で普及しつつある「制震工法」の部材から、振動を抑えることは自然な流れです。テープ、オイルダンパー、高粘性ゴムなどが、微妙な揺れを吸収する役割を果たします。下階の天井、壁や空気から伝わる振動を最小限にすることで、下階の人に不快な思いをさせない機能となるのです。分譲マンションでは、遮音性能が良いか、悪いかで売れ行きが変わってしまうので、研究も進んでいるはずです。航空機業界や自動車業界も遮音性能には苦労しているはずです。そんな彼らが本格的に、木造建築の遮音に力を注いでいただけると、驚くほど進化するのではないかと思うのです。始まったばかりですが、各建材メーカー単独でなく、ゼネコンやハウスメーカーなどが力を合わせ、木造建築用の設計手法を開発しつつあるのは、うれしい限りです。

どのような部材でも、メリット・デメリットがありますが、なんといっても、木材は日本の国土には沢山あり、その利用が欠かせません。植林すれば、再生できる部材でもあり、地球環境への貢献度も高い。だからこそ、いろいろな業界関係者が力を合わせ、木材のデメリットを最小限に抑える技術が開発されてほしいと願っています。木造建築が普及するためにも、どんどん参入してきてほしいものです。