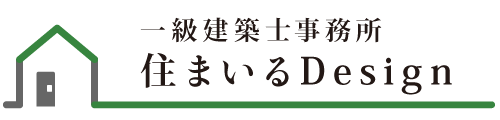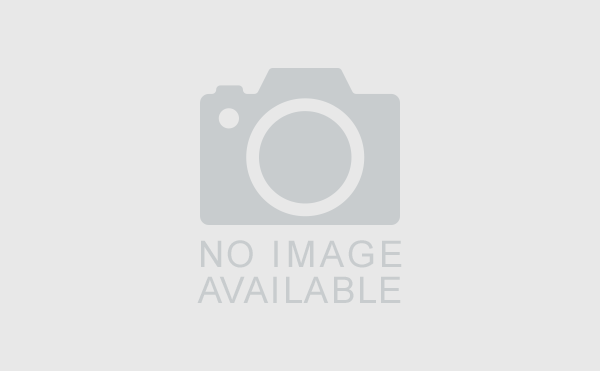今後の建材商材に期待したい

40数年前、住宅業界に飛び込み、現場監督、住宅設計や土地の仕入れ、販売など一通り経験してきました。また、住宅だけでなく、共同住宅(マンション、アパート)、貸店舗、大震災後の仮設住宅など木造建築でできる建物は、ほとんど手掛けてきました。この40年で、木造建築の作り方や建材など大きく進化してきたのは言うまでもありません。
.jpg)
第一に、在来工法のプレカット加工の普及でしょう。大工の手加工から、CAD、構造計算などが付随して構造の精度、安定供給が可能になった。構造躯体の加工を大工工事から、離すことによって業界の生産性が大きく変わったのだ。同時に普及し始めた集成材も構造の強度に貢献してきました。次に、建材や設備も進化したことで快適な空間づくりに効果を上げている。浴室のユニットバス、トイレのウオシュレット、熱交換型の換気システムなどは、40年前の戸建住宅には存在もしていない。今は、搭載率90%以上と言って良いでしょう。
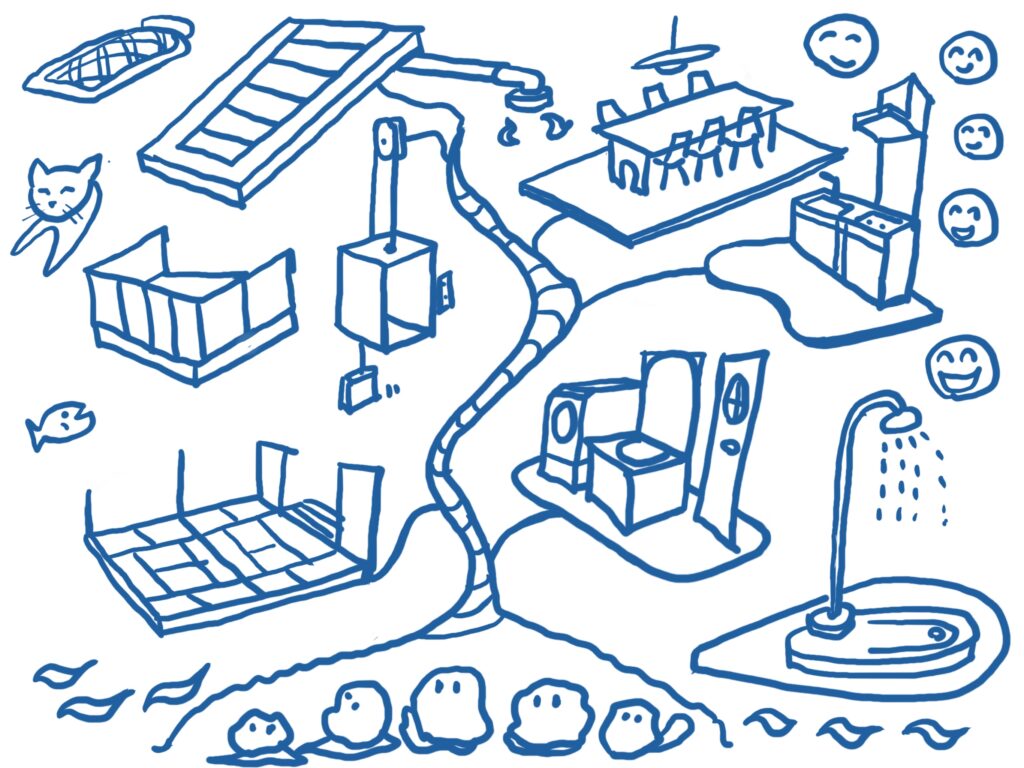
一方、40年前から進化していないこともある。まずは、住宅ローンという金融商品だ。高度成長時代に住宅を持つために必要な仕組みであったが、新築供給過剰、低金利、低収入など今の時代になど合っているのか不安を持つ。土地を開発して分譲住宅という供給システムも、40年前と同じ、未だにあり続けている。分譲マンションの区分所有権という考え方は、高度成長時代に作られた仕組みであり、このままでは、社会問題を引き起こさないのだろうかと心配である。

日本の住宅は、今後どのように進化してくのでしょうか、この10年でどのようになるのか、私見ですが纏めてみました。ハード面では、第一に繰り返しの地震がこれだけ多くなると、木造建築は、耐震性能だけでなく「制震部材」の搭載が当たり前になるでしょう。普及し始めれば、さらに価格もリーズナブルになり、地震対応性能も消費者に受け入れられるはずです。二つ目は、ペロブスカイトの太陽光発電によって、住宅のエネルギーの在り方が変わり、車のエネルギーも自宅供給が可能になるのではないかと思うのです。三番目が、木材の利用方法です。木材のデメリット(腐朽、耐火、害虫など)を解決し、躯体だけでなく、内装や外装へ採用する建築物が一般化されると思われる。なんといっても日本の木材資源は豊富にあるから利用しない手はないのです。ソフト面では、「稼ぐ家」「働く家」など、「子育て」だけでない機能を持っている住宅に変わるでしょう。特に、職住を同時に享受できる快適な住まいだ。働きやすい家、熟睡できる家などがコンセプトになってくると思われる。また、住宅ローンのような年収で借り入れが決まるのではなく、稼ぐ家(太陽光、賃貸、職場料)での収支が求められるようになってくる。また、「将来にどのように利活用ができる家なのか」などが借り入れにも要求されるようになるでしょう。地球貢献や解体費用も加味するようになれば、木造建築の優位性がより明確になる時代が、直ぐそこまで近づいています。もう一つ、二拠点居住が一般的になってくると、住まいが求められる機能も、各々の住まいで大きく変わってくるため、二極化するでしょう。どちらの家にも、安全性能は必要不可欠だが、消費者の生活スタイルによって収納や設備(浴室やキッチン)の機能が大きく変わるということです。 性能や機能といったものは、一般的に「新築住宅」が先導し、その後「既存住宅」が追いかけていきます。取り残されていく住宅もあるでしょうが、既存住宅が社会インフラ財産の一部とがんがえると、所有者任せでは限界を感じるのです。国民に「住宅は、社会インフラ」との認識が根付けば、公共性を持つのだから、公金の投入もしていかなければならないと考えます。地震で被害が無くなれば、避難所や仮設住宅も準備しなくていいし、省エネルギー住宅になれば、エネルギー問題や温暖化に関する対策費を少なくすることができます。社会全体から見れば、地震保険料も少なくすることが可能です。住まい手にも、国や行政庁にもメリットのある住宅業界にしていきたいものです。