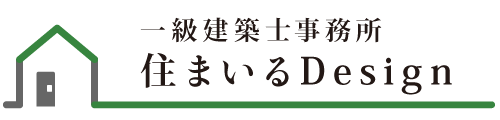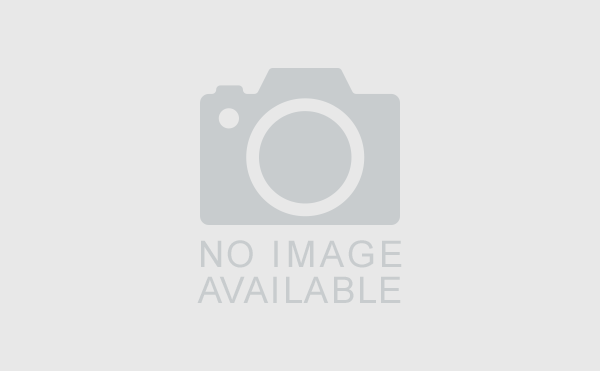住宅着工が激減の中
今年度に入って、3カ月間の新設住宅着工戸数が公表されています。着工戸数の減少を予想してはいたものの、これほど大きな落ち込みになるとは驚きです。このまま持ち直さなかったら、60万戸台になってしまうのではないかと思うほどの水準です。着工戸数に依存しているプレカット工場や、基礎工事会社、地盤改良会社などは、特に影響が大きいのではないでしょうか。しかし、彼らは予想していましたから、非住宅建築の受注を目指し、設計事務所や木造ゼネコンへの営業だけでなく、住宅会社へ受注方針の変更も促しています。うまく対応して軌道に乗っている会社もあれば、残念ながら時代に飲み込まれている会社も多くいます。

私たち地域に根差す工務店は、地域のためにも生き残っていかなければなりませんが、新築住宅だけでは消費者から認めてもらえない時代になってきています。住宅会社としては、新築に頼らなくても生きていく道はたくさん存在します。なにより、地域の消費者が望んでいること、不足していること、喜んでいただけることは何かを考えて、提案することではないでしょうか。
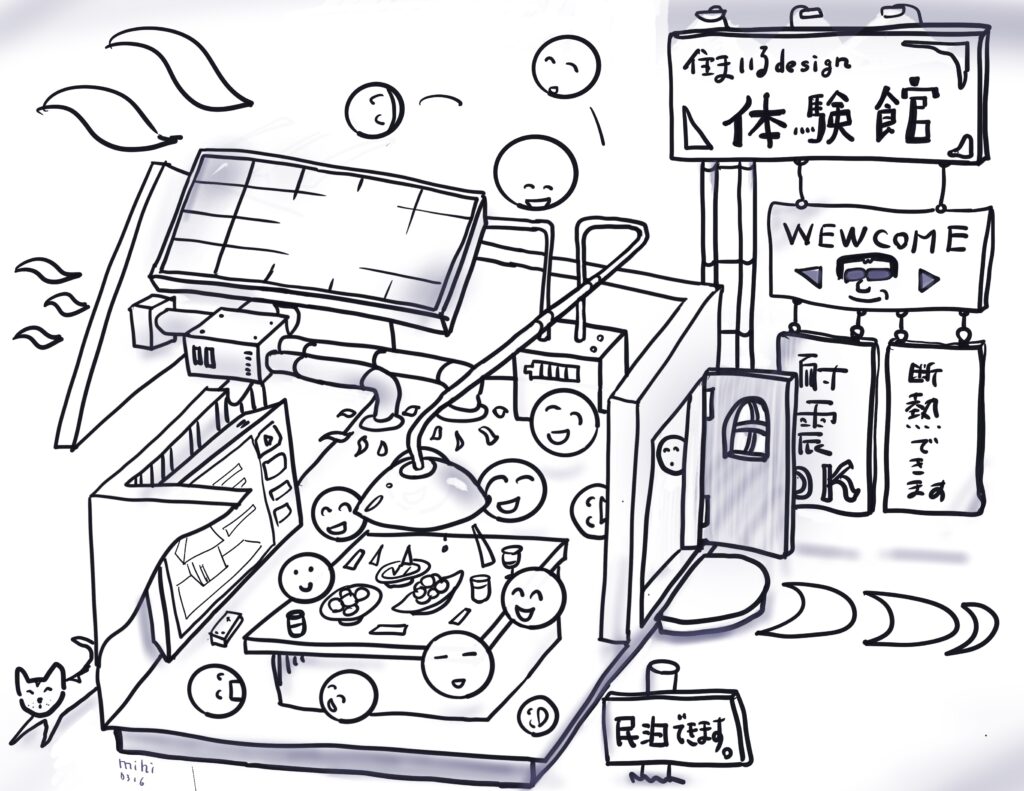
まずは、これから必ず伸びていく買取再販ビジネスの支援です。このビジネスの実績を見ると、取引される住宅の築年数の平均が28年となっています。そうなると、2000年以降に普及し始めた、「住宅性能評価」を受けた住宅がどんどん市場に出てくると予想できます。大手だけでなく、中小の不動産会社にとっても、ビジネスの一つの軸足になりつつあり、新築分譲住宅と比較して価格が魅力的になれば、第一次購入層が一気に動き始めてくるはずです。そうなると、それらのリノベーションや修繕工事が今まで以上に増えるはずですから、不動産会社の下請けになるのではなく、付加価値をつける設計工事力をつけ、私たちがコントロールできるようにならなければなりません。さらに、住宅から住宅への改修だけでなく、住宅からグループホーム、ゲストハウス、店舗併用など、利活用を変える提案ができれば、情報を持つ不動産会社からの信頼を得ることができます。また、上記のようなリノベーション不動産は、「耐震診断・補強工事」「断熱改修」の知識や技術力が差別化に繋がるので、二つの能力は身に付けるべきと考えています。

その次に、住宅業界に大きな影響を与えると思われるのが、二拠点居住というライフスタイルです。これは、何が何でも日本に普及させる必要があります。先の参議院選挙の政策やテレビなどでも、特集が組まれるようになってきました。空き家問題と日本人の生活、地震大国、省エネ環境といった日本の課題を考えるとき、解決策の一つになると考えるようになってきたからです。私たちが行うことは、自社の商圏だけで良いので「住宅や建築物」の状況を知ることです。できれば、最低限の住戸データベースを持ち、どこに存在しているのか、空き家なのか、築年数くらいは把握しているようにしましょう。また、住まい手の情報もデータとして残しておくと、次の展開が図れますが、私たち以上に地方行政庁がそれらのデータを持つことになるでしょう。大きな課題は、都市に住む消費者とそれらの物件を如何にマッチングさせるかです。地方行政も、お試し体験会や住民との交流会など工夫はしていますが、民間がもっと積極的に入り込まないと進まないのです。二拠点生活を満足させるためには、二拠点目の住まいの価値をどこまで高められるかであり、住宅会社の役割の一つになってくるでしょう。

これからの日本の住宅業界や建築業界は、既存のものを如何に利用し、価値を高められるかが重要になります。折角持っている住宅や土地といった財産を今後どう活用するのか。また、修繕だけでは納得できない消費者も多く存在しており、自分たちのためだけでなく、日本社会の中で利活用できるか、提案を望んでいると感じます。