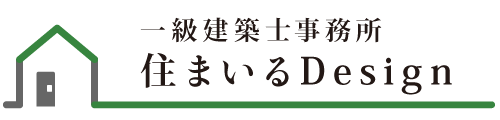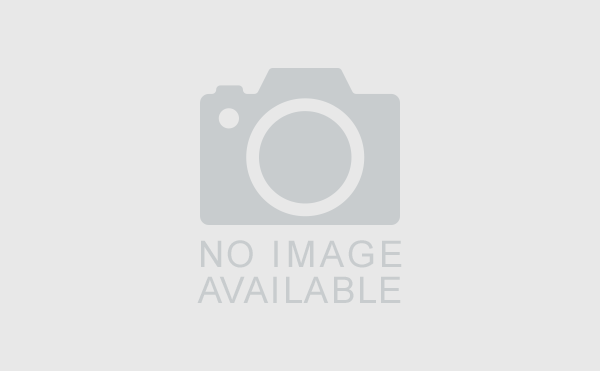人材不足というが

人材不足といわれるなか、各企業が中途採用を強化していることもあり、リクルート仲介業は予想以上に伸びている業界の一つになりました。人材が流動化している社会情勢を考えると、これからも伸びていくのでしょう。企業にとって、人材採用のための費用がこれからも増えていくのでしょうが、中途採用にかける費用負担があまりにも大きくなり、疑問を感じますね。

新規採用は、企業が成長する以上必要だと考えています。しかし、今いる人材が、もっと活躍し、業績に貢献できるように、教育やシステムに費用をかけるべきではないでしょうか。人材が流動化することは、「個人の能力を十分に発揮できない」「給料や福利厚生が不十分」といった課題を抱えているからです。どうしても他社と比較され、他社に同調しないと人材が集まらなくなっており、中小企業は経営を圧迫されるとわかりつつも対処するという、頭の痛い深刻な問題になっています。従業員一人ひとりの生き方は、数年前とは違うとわかっているにもかかわらず、企業は一般的な対応を繰り返し、その一方、残念ながら社員は一般的な対応だけでは満足できず、辞めていってしまうのです。そのため、企業は再度、新たな人材を採用する必要に駆られ、費用をどんどん掛けるという、悪循環が生まれています。

若い社員の立場で言うと、「収入、休暇、福利厚生」が重要であり、「やりがい、生きがい」を仕事に求める人が少なくなっています。収入も、生活ができ、少し遊べる程度には要望するが、必死になって稼ごうとする人は少なくなりました。本来、「仕事」は自分を人間として成長させるために必要不可欠なのでしょうが、それに気づく人は少なくなってしまったようです。自らの将来を見据え、成長していくために転職をするならいいのですが、目の前の条件や人間関係だけを見て、転職している人が多くいると感じるのです。ですから、生涯、何回も何回も転職する人が増えているのではないでしょうか。しかし、そのような状況にあわせ、中小企業の経営者の方が、考え方や育て方を変えていかなければならないのです。私が提案するのは、

- 企業の社会的存在価値を明確にすること
- 経営者自らが人間学を学び続けること
- 社員の潜在能力を信じること
- 個々の「楽しい(ラクではない)こと」を実現支援すること
- 小さな分野・範囲で主役(オーナーシップ)にすること
- 個人の行動と企業経営を結び付ける、などではないでしょうか。
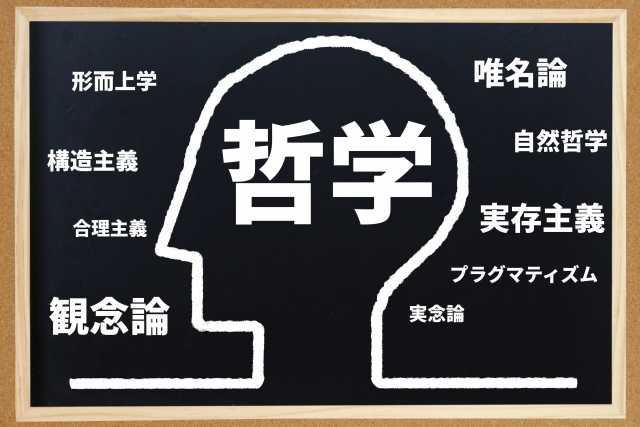
例として、ハウスメーカーである土屋ホームの創業者の土屋公三氏は、個人・家庭・会社の生涯幸福設計を一致させることが重要であり、その実現のために「3KM」手帳を持たせていたといいます。素直にやり続けている社員もいれば、形だけになってしまう社員のいるのでしょうが、そのような仕組みを持つことは大切なことです。稲盛和夫氏は、創業時から社員との会食を積極的に行い、社員一人ひとりの生き方や考え方を聞いており、そのうえで、京セラフィロソフィを徹底していたといいます。

組織は、人が集まって構成されるものです。一人ひとりは全く違う個性を持っていることは言うまでもなく、将来像も違うはずです。それを認めるかどうかなのでしょう。それを企業として応援できるかです。中小企業は、誰でもない、経営者自らが社員を採用したのであり、一緒に組織を構成する以上、彼らを信じて業績に結び付けるしかないのです。それをつくり上げることができないのであれば、「中途採用費用が永遠に発生することを覚悟するしかない、私のような「ひとり」で行い組織をつくらなければいい」と開き直るわけにいかないので、人材不足を感じている企業は、社員教育やシステムを変えていくしかないということでしょう。