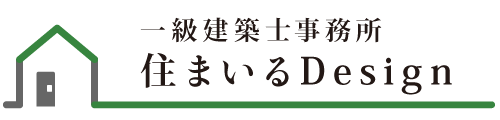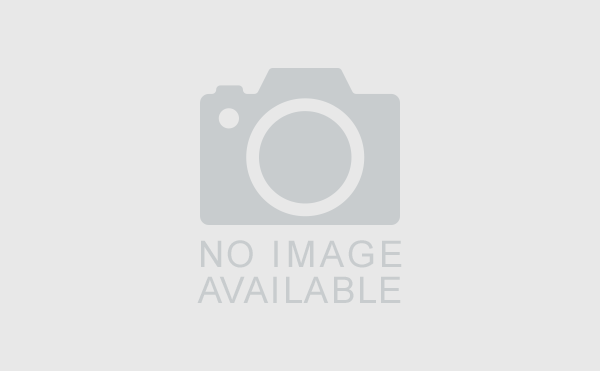ビジネス経営者と読書
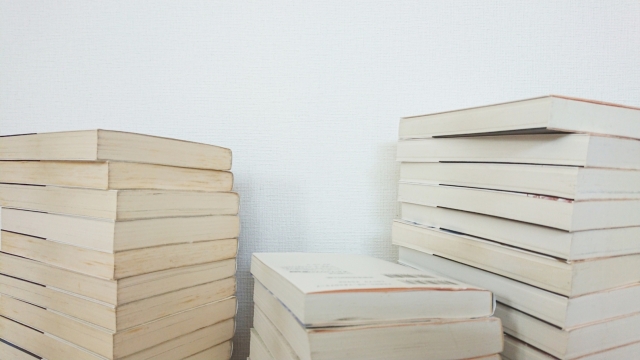
最近、本を読むことが少なくなっていることに、不安を感じています。サラリーマン時代は、単身赴任でしたし、電車通勤、更に飛行機での出張も多く、年間100冊近く読んでいました。「木鶏クラブ」という、読後感を話し合う会を運営していたことも理由の一つです。ところが、起業してからは車や自転車での移動が多く、横浜まで行かなければならない「木鶏クラブ」への参加も減ってしまいました。また、自宅や事務所にいるときは、ユーチューブやネットフリックス、BS、タイムシフトなどを観る機会が多くなり、本を読むのはわざわざ図書館まで足を運んでとなってしまいました。
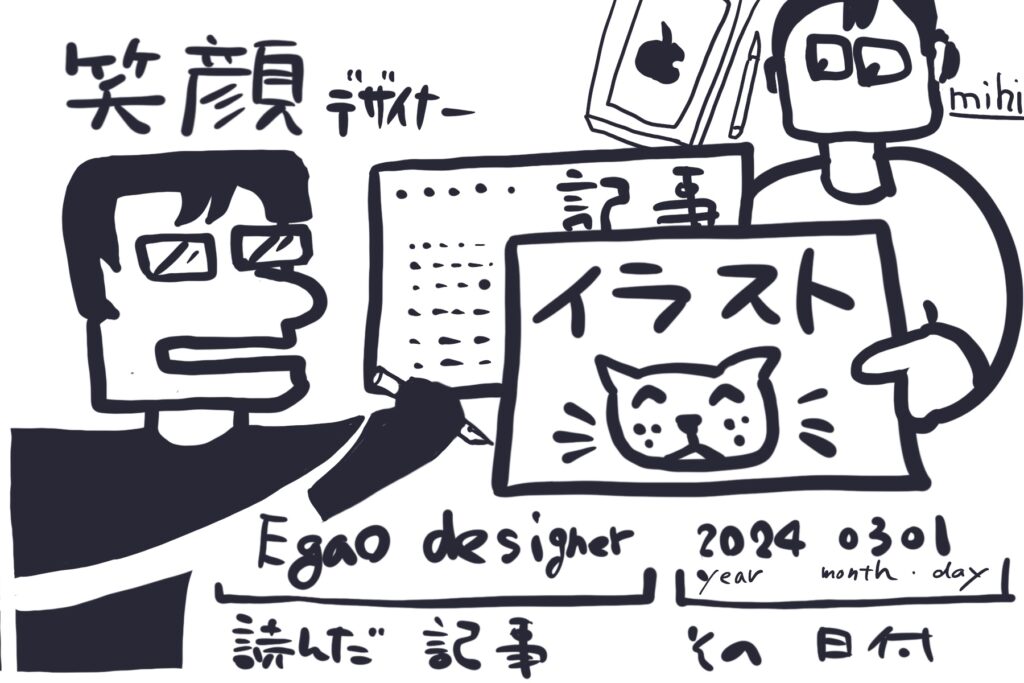
言うまでもなく、本は著者が研究や経験からノウハウを纏めたものです。たった1,500円程度の投資で、ビジネスでも生き方でも、健康的な課題も解決の道を明示してくれます。著名な経営者のほとんどが、本を良く読み、自らの経営に生かしています。稲盛和夫や渋沢栄一などの日本人だけでなく、ビル・ゲイツやジョブズといったIT経営者でさえ、読書を欠かすことはなかったといいます。良き経営者の読書は、「何を読むかより何故その本を読むか」「ビジネスや人生にいかに生かすか」といった目的をもっているというのです。今ある課題をどうすれば解決できるか、そのためのヒントを探すために読書をする。アウトプット、効果を意識するから、何冊も読めるらしいのです。
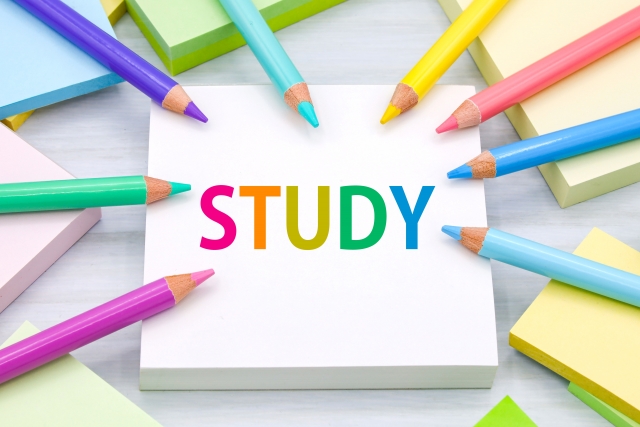
多読をしないと目的の本を探せないことも確かですが、本の中に出てくる推奨本を次々と読む方法もあります。その中で、運命の一冊に出会うことができると思っています。そして、運命の本と出会えば、座右の銘として繰り返し読むことはそれほど難しいことではないですね。経営者として組織を活性化させ、ビジネスを順調に進めるためには、課題が次から次へと出現することは言うまでもありません。運命の本と出会うチャンスは、「人生やビジネスで最も悩んでいる時」、また、「何が何でもかなえたい夢がある」や、「寝ても覚めても湧いてくる憧れ」といった状況です。つまり、ピンチやワクワク感が起きている、あるいは自ら起こすことが大事なのですね。私の場合、定年退職したこともあり、組織の運営や新規ビジネスなどの課題が少なくなってきたこと、人間関係のストレスなどもずいぶん少なくなったことが、読書量を減らしているのかもしれません。人生の運命の一冊と出会えないのは、困っていない、悩んでいないからでしょうか。だからこそ、ワクワクの状況をつくっていかなければと思っています。

例えば、 25年くらい前、N社で商品開発やビジネスモデルを作成する担当する部署に移った時の私の経験です。「寝ても覚めても」といった状況だったと記憶しています。図書館やブックオフで本を探していたのですが、「どうしたら売れるのか」といった題名の本を読み、「これだ!面白い」と感じ、その著者の本をかき集めたことを思い出します。著者である商売科学研究所の伊吹卓氏は、阪急の小林一三氏、松下幸之助氏、グリコの江崎利一氏を取材して、商売の法則を導きだしたというのです(詳細は4月10日更新「商品開発の販売」https://ys-s-design.com/blog/2025/04/10/%e5%95%86%e5%93%81%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%a8%e8%b2%a9%e5%a3%b2/)。そして、著者の本をできる限り読み漁り、休日を取ってまで大阪事務所へ会いに行きました。伊吹氏もすでに高齢になっていましたが、親切にいろいろ話をしていただいたのです。その後のビジネスに大いに役立ったことは間違いなく、住宅会社や工務店の商品開発のコンサルなどに組み込むことができたのです。インターネットで情報や知識を得ることはできますが、それだけではなかなか行動に移せないものです。行動して初めて成果につながるのがビジネスです。その行動を促す感動やモチベーションは、本との出会いから生まれることが多いと思うのです。著者の人間性も大きく影響しており、本と同時に著者を「やっと見つけた、発見した」といった感動が、知識や情報から行動へ変えていくことができます。中小の企業のトップほど、自社の業績に大きく影響するはずですから、悩みを解決し、ワクワク感を達成するためにも、読書からヒントを得て、行動に移すことを願っています。